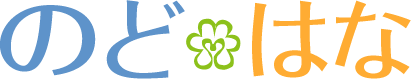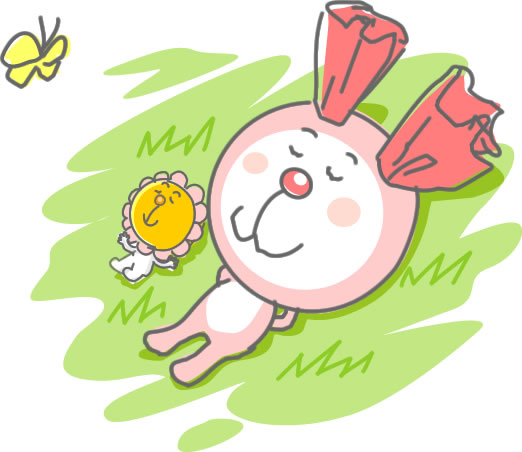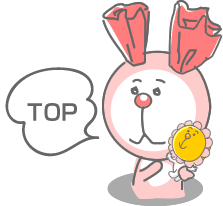のど・はなに良い薬膳レシピ
季節や体調に合わせた、
のどにおすすめの食材を使用した薬膳レシピをご紹介します。
監修:一般社団法人国際発酵食医膳協会 代表理事、「和薬膳療法士・伝統発酵醸師師範」 河合 由記
~「食べる」を見直したら「内側から美しい生き方」が見えてきたを合言葉に食医膳と発酵食を広く伝えている~
河合 由記 先生のサイトURLhttp://fodfex.com/
薬膳とは
薬膳とは、漢方の考え方に基づいて、季節や体調に合わせて食材を選んで作る料理のこと。中国には、食材にも薬と同じようにからだを治す効果があるという「医食同源(いしょくどうげん)」という考えがあります。近代になって、この考え方に基づく料理を「薬膳」と呼ぶようになりました。
薬膳を実践するには、まず食材の持っている性質や味を知ることが大切です。また、薬膳料理は、即効性のある薬とは違うため、同じ食材を1~3日食べつづける必要があります。ただし、食べ過ぎは、逆にからだに毒となるため、自分の体調をみながら食べるようにしましょう。
秋の薬膳
のどを潤し、乾燥から守るカリンはちみつ茶
冬に向かって空気が乾燥してくる時期です。乾燥による咳や風邪対策に、肺を潤すカリンのはちみつ漬けを作り置きしておくと便利です。あたたかいお湯に溶かして湯気を吸いこみながら、1日何回かに分けて飲むと効果的です。

材料(数杯分)
-
- カリン
- 1個
-
- はちみつ
- 500ml程度
-
- 保存用のビン
- (容量500ml)
- のどにいい食材
-

カリン
- 作り方
-
 生のカリンをきれいに洗い、皮をむかずにそのまま5mm程度の厚さにスライスする。
生のカリンをきれいに洗い、皮をむかずにそのまま5mm程度の厚さにスライスする。 ①を500ml程度の大きさのビンに入れ、カリンがしっかり浸かるまでハチミツを注ぐ。
①を500ml程度の大きさのビンに入れ、カリンがしっかり浸かるまでハチミツを注ぐ。 ②を1ヶ月ほど冷蔵庫で保存。カリンからエキスが出たら飲みごろ。
②を1ヶ月ほど冷蔵庫で保存。カリンからエキスが出たら飲みごろ。 飲むときは、③からカリンの実と汁の適量をカップに取りわけ、お湯を注いで溶かす。
飲むときは、③からカリンの実と汁の適量をカップに取りわけ、お湯を注いで溶かす。
- 調理&摂取ポイント
- カリンを漬け込むときは、はちみつをビンの口いっぱいまで入れて、なるべく酸素が入らないようにしましょう。ビンを開封したら、冷蔵庫で保存し、2ケ月くらいで飲み切るようにしましょう。
のどの乾燥を防いでからだもホカホカ!生レモンたっぷりレモネード
レモンは、のどの粘膜を潤し、代謝を高める効果があるだけでなく、ビタミンCが豊富で免疫力もアップさせる食材です。かぜの引きはじめやのどに不調を感じたら、からだをあたためて発汗を促すしょうがと、肺を潤してせきを止めるはちみつを一緒に摂取しましょう。

材料(2人分)
-
- レモン
- 2個
-
- はちみつ
- 大さじ2~3
-
- お湯
- 50ml
-
- 生姜のすりおろし
- 小さじ1
- のどにいい食材
-

レモン 
はちみつ 
しょうが
- 作り方
-
 レモンの果汁をしぼる。
レモンの果汁をしぼる。 はちみつとよく混ぜて、お湯50mlを加えてよくまぜる。
はちみつとよく混ぜて、お湯50mlを加えてよくまぜる。 しょうがをすりおろし、②に加えてまぜる。お好みの濃さになるまでお湯(分量外)を注ぐ。
しょうがをすりおろし、②に加えてまぜる。お好みの濃さになるまでお湯(分量外)を注ぐ。
- 調理&摂取ポイント
- しぼったレモンは、ビタミンCが失われないうちに、なるべく早く飲むようにしましょう。すっぱいと思う人は、飲みやすいようにお好みではちみつを足してください。冷え症の人は、生のしょうがよりも干したしょうがを使うとさらに効果的です。また冷え症の人は、しょうがの飲みすぎはかえってよくありませんから、適量を取るようにしましょう。
さわやかな香りでのどの痛みをとる菊花&ミントティー
日本では昔から食されてきた菊は、からだの熱を取る効果があるといわれています。同じように、ミントは気の流れをよくしつつ、解毒・解熱作用があるので、熱があるときに適しています。また、清涼感のあるさわやかな味わいで、のどの腫れや痛みの改善にもおすすめです。

材料(1人分)
-
- 菊花(乾燥)
- 3g※生の菊なら3、4輪
-
- ミント
- 指先で3つかみ
-
- はちみつ
- 適宜
- のどにいい食材
-

ミント 
菊花(乾燥又は生) 
はちみつ
- 作り方
-
 ポットに菊、ミントを入れて、沸きたてのお湯を注ぐ。
ポットに菊、ミントを入れて、沸きたてのお湯を注ぐ。 3~5分ほど置いて成分を抽出する。
3~5分ほど置いて成分を抽出する。 カップに注いで、はちみつを加える。
カップに注いで、はちみつを加える。
- 調理&摂取ポイント
- 乾燥した菊花を使う場合は、菊がふやけるまでポットの中でよく蒸らしましょう。菊とミントの成分がお湯に十分でてくるまで待ってから飲むようにしてください。お湯の色が薄いグリーンになるくらいが飲みごろです。はちみつはお好みの甘さになるよう加えてください。
プルプル&ホクホクの食感が楽しい五味子(ゴミシ)ゼリーと蓮の実あんの2色パフェ
乾いたせきがなかなか止まらないときは、肺を潤す五味子と蓮の実がおすすめです。五味子のさわやかな酸味と、蓮の実のホクホクとした食感が楽しいパフェなら、なかなかお薬が飲めないお子さんも食べやすいでしょう。一緒に食べるくだものには、のどや肺を潤すぶどうや梨、咳やたんを鎮めるびわ、ビタミンがたっぷりのイチゴなどがおすすめです。

材料(2人分)
-
- 五味子
- 20~30g
-
- 水
- 400ml
-
- 黒砂糖
- 約20g
-
- かんてん粉
- 4g
-
- 蓮の実
- 50g
-
- 生クリーム
- 50㏄
-
- ぶどう(季節のくだものでもよい)
- 2粒
- のどにいい食材
-

五味子 
黒砂糖 
蓮の実
- 作り方
-
 五味子をさっと水洗いし、400mlの水に半日ほど浸しておく。
五味子をさっと水洗いし、400mlの水に半日ほど浸しておく。 蓮の実も半日ほど水に浸しておき、柔らかくなったら水を捨てる。蓮の実はふやけたら、中心にある芽を取り除く。
蓮の実も半日ほど水に浸しておき、柔らかくなったら水を捨てる。蓮の実はふやけたら、中心にある芽を取り除く。 ①を鍋に入れ、かんてんを加えてよく混ぜる。火にかけて沸騰させ、かんてんが溶けたら火を止めて器に流し込む。
①を鍋に入れ、かんてんを加えてよく混ぜる。火にかけて沸騰させ、かんてんが溶けたら火を止めて器に流し込む。 ③の容器を冷水につけて、粗熱を取って固める。
③の容器を冷水につけて、粗熱を取って固める。 ②を鍋に入れ、蓮の実の3倍ほどの深さまで水を加える。火にかけ、水が3分の1程度になるまで煮詰めたら、黒砂糖を加えて、焦がさないように気をつけながら水がなくなるくらいまで煮詰める。
②を鍋に入れ、蓮の実の3倍ほどの深さまで水を加える。火にかけ、水が3分の1程度になるまで煮詰めたら、黒砂糖を加えて、焦がさないように気をつけながら水がなくなるくらいまで煮詰める。 ⑤をミキサーにかけ、少しペースト状になってきたら、生クリームを少し加えて再度ミキサーにかける。よく混ざったら、残りの生クリームを加えてさらに混ぜる。
⑤をミキサーにかけ、少しペースト状になってきたら、生クリームを少し加えて再度ミキサーにかける。よく混ざったら、残りの生クリームを加えてさらに混ぜる。 ④のゼリーが固まったら、⑥を上に盛り、好みで季節のくだものを飾る。
④のゼリーが固まったら、⑥を上に盛り、好みで季節のくだものを飾る。
- 調理&摂取ポイント
- 五味子はお湯で戻すと苦みが出てしまうので、水に浸し、半日かけてゆっくり戻しましょう。蓮の実の中にある芽は苦みの原因になります。水を吸って柔らかくなったら、実を割って、しっかり取り除くようにしましょう。
せきを抑えて肺を潤すホクホクごはん銀杏&百合根のごはん
空気が乾燥し始めるこの時期は、のどのイガイガが気になったり、せきが出でやすくなります。そこで、肺や気管を潤し、不足している体液を養う働きのある百合根と、肺の働きを助け、せきをしずめる銀杏を合わせて摂りましょう。

材料(茶碗4杯分)
-
- 銀杏
- 30粒程度
-
- 米
- 2合
-
- 百合根
- 40g
-
- 水または昆布出汁
- 400cc
-
- 塩
- 少々
※昆布出汁とは、水に乾燥昆布を入れて一晩おいたもの
- のどにいい食材
-

銀杏 
百合根
- 作り方
-
 銀杏の殻をむいてゆでる。銀杏の色がきれいな緑色にかわって、薄皮がむけてきたら茹であがり。お湯から取り出し、水気を切っておく。
銀杏の殻をむいてゆでる。銀杏の色がきれいな緑色にかわって、薄皮がむけてきたら茹であがり。お湯から取り出し、水気を切っておく。 お米と一口大に切った百合根を炊飯器に入れ、昆布出汁と少量の塩を加えて炊く。
お米と一口大に切った百合根を炊飯器に入れ、昆布出汁と少量の塩を加えて炊く。 炊きあがった(2)に(1)を混ぜる。
炊きあがった(2)に(1)を混ぜる。
- 調理&摂取ポイント
- 銀杏は、ゆでているときにおたまを使って鍋の中でコロコロ転がすと、薄皮がきれいにむけます。ごはんを炊くときは水でもかまいませんが、せきやたんを鎮める効果がある昆布の出汁を使うとより効果的でおいしく炊きあがります。
栄養と旨みを凝縮してからだを冷やさない温野菜サラダ蒸し野菜の黒ごまソースがけ
寒さと乾燥から、かぜを引きやすくなる時期です。肺をうるおす長いも、粘膜を強くするかぼちゃ、せきを止めるだいこん、血を補う事でからだに潤いを与えるにんじんを蒸すことで、栄養も旨みもしっかり摂りましょう。さらに味付けには、肝腎を養う事で季節柄からだに不足しがちな潤いを与える黒ごまやからだを温める黒砂糖で作ったソースがおすすめです。

材料(2人分)
-
- 長いも
- 直径約5cm×長さ約6cm
-
- かぼちゃ
- 50g
-
- 大根
- 50g
-
- にんじん
- 50g
黒ごまソース
-
- 練り黒ごま
- 大さじ2
-
- お湯
- 大さじ1
-
- 黒砂糖
- 小さじ1
-
- しょうゆ
- 小さじ1/2
- のどにいい食材
-

長いも 
かぼちゃ 
大根 
にんじん
- 作り方
-
 練り黒ごまに、分量のお湯を加えてよく混ぜ合わせてから、黒砂糖、しょうゆを合わせて、黒ごまソースを作る。
練り黒ごまに、分量のお湯を加えてよく混ぜ合わせてから、黒砂糖、しょうゆを合わせて、黒ごまソースを作る。 大根、にんじんを一口サイズの乱切りにする。かぼちゃは、皮の固い部分をむいてから、3cm角ぐらいの食べやすい大きさに切る。長いもは、きれいに洗って皮をむかずに1.5~2cm幅に切る。
大根、にんじんを一口サイズの乱切りにする。かぼちゃは、皮の固い部分をむいてから、3cm角ぐらいの食べやすい大きさに切る。長いもは、きれいに洗って皮をむかずに1.5~2cm幅に切る。 ②の材料のうち、大根とにんじんを蒸し器に入れて10分ほど蒸す、その後にかぼちゃと長いもを入れてさらに20分ほど蒸す。材料にお箸がすっと通るようになったら火を止める。
②の材料のうち、大根とにんじんを蒸し器に入れて10分ほど蒸す、その後にかぼちゃと長いもを入れてさらに20分ほど蒸す。材料にお箸がすっと通るようになったら火を止める。 ③を皿に盛り、食べるときに①を回しかかける。
③を皿に盛り、食べるときに①を回しかかける。
- 調理&摂取ポイント
- 長いもの皮には細かいひげがあるため、ひげが気になるときはコンロで軽くあぶってください。細かいひげの部分だけが焼けて、手で払うだけでパラパラと落とすことができます。また、野菜を蒸すときは、しっかり蒸すと甘みが増しておいしくいただけます。
からだを温めて気を巡らし免疫力を高めるえび、くるみ、にら、長ねぎの炒め
からだが冷えると免疫力がさがり、かぜやインフルエンザウイルスにかかりやすくなってしまいます。そこで、からだを温める食材を積極的に摂りましょう。腎の働きを高めからだを温めるえびやニラ、肺の機能を高めるくるみ、からだを温めて気の巡りをよくする長ねぎに、寒気やのどの痛みを鎮める菊花、肺をうるおす枸杞の実を合わせて、からだに冷えを入れないように気をつけましょう。

材料(3人分)
-
- えび
- 6尾
-
- くるみ
- 適宜
-
- 長ねぎ
- 1本
-
- にら
- 1束
-
- 菊花
- 少々
-
- 枸杞の実
- 少々
-
- 胡麻油
- 少々
-
- 塩
- 少々
- のどにいい食材
-

えび 
くるみ 
長ねぎ 
にら 
菊花 
枸杞の実
- 作り方
-
 長ねぎは約5mm幅の斜め切りに、ニラは約3cmの長さに切っておく。
長ねぎは約5mm幅の斜め切りに、ニラは約3cmの長さに切っておく。 えびの背綿を取ってよく洗い、酒をふりかけ、塩と片栗粉をまぶしておく。
えびの背綿を取ってよく洗い、酒をふりかけ、塩と片栗粉をまぶしておく。 くるみを軽くフライパンで炒っておく。
くるみを軽くフライパンで炒っておく。 フライパンに胡麻油を入れて温めてから、長ねぎとにらを炒めて塩で味付けし、皿に盛る。
フライパンに胡麻油を入れて温めてから、長ねぎとにらを炒めて塩で味付けし、皿に盛る。 フライパンでえびを炒める。えびを皿に上げる直前に、くるみをあえる。
フライパンでえびを炒める。えびを皿に上げる直前に、くるみをあえる。 ⑤を④の上に盛りつけ、最後に軽く水洗いした菊花と枸杞の実を飾る。
⑤を④の上に盛りつけ、最後に軽く水洗いした菊花と枸杞の実を飾る。
- 調理&摂取ポイント
- えびは、臭みをとるために塩水で十分洗ってから、キッチンペーパーなどで水気をしっかりとりましょう。少しお酒を振りかけてから片栗粉をまぶすとさらに臭みが気にならなくなります。また、えびは炒めすぎると固くなるので、火加減に気をつけましょう。
肺を潤しながら秋の味覚を味わって梨と白きくらげのコンポート
秋の果物である梨は、肺を潤し、熱やのぼせなどの熱症状を改善し、のどの乾燥や粘り気のある「たん」、「せき」、のどの炎症といった、のどの不快症状を和らげます。さらに、肌や粘膜を潤すといわれる白きくらげと、肺を潤しながらせきを鎮めるはちみつを合わせると相乗効果が期待できます。

材料(2人分)
-
- 白きくらげ
- 3g(乾燥時)
-
- 梨
- 1/2個
-
- 水
- 2カップ
-
- レモン汁
- 大さじ1
-
- はちみつ
- 大さじ1
- のどにいい食材
-

梨 
白きくらげ 
レモン 
はちみつ
- 作り方
-
 白きくらげは、よく洗って30分以上水に浸して戻す。戻している水が濁るようなら途中で水を取りかえ、根元の固い部分は取り除く。十分やわらかくなってから、手でひと口大にちぎる。
白きくらげは、よく洗って30分以上水に浸して戻す。戻している水が濁るようなら途中で水を取りかえ、根元の固い部分は取り除く。十分やわらかくなってから、手でひと口大にちぎる。 梨は皮をむき、縦に8等分にカットしたあと、7ミリ程度の厚さのいちょう切りにする。鍋に白きくらげと水2カップを入れて火にかける。沸騰したら弱火にして、トロミが出てくるまでじっくり煮る。
梨は皮をむき、縦に8等分にカットしたあと、7ミリ程度の厚さのいちょう切りにする。鍋に白きくらげと水2カップを入れて火にかける。沸騰したら弱火にして、トロミが出てくるまでじっくり煮る。 ②に梨を加えて、さらに水が少なければ適量を足してから、梨がやわらかくなるまで煮る。火を止めて、レモン汁、はちみつを加えてよく混ぜる。
②に梨を加えて、さらに水が少なければ適量を足してから、梨がやわらかくなるまで煮る。火を止めて、レモン汁、はちみつを加えてよく混ぜる。
- 調理&摂取ポイント
- 白きくらげは、最短でも20~30分、できたら1時間ほどじっくり煮続けると、白きくらげの中の植物性コラーゲン質が十分取り出せます。
また、レモンは、ビタミンCが失われないように、火を止めてから加えましょう。ラップを使って、
表面がなるべく空気に触れないようにしながら冷蔵庫で保管すれば、2、3日は保存できます。どうしても時間のない人に!~梨の簡単アレンジレシピ~
梨を横半分にカットし、種をスプーンなどで取りのぞき、そこへハチミツを大さじ1入れて蒸し器で20分ほど蒸す。梨が柔らかくなったらできあがり。常温にさましてから食べる。